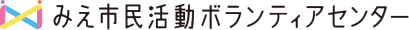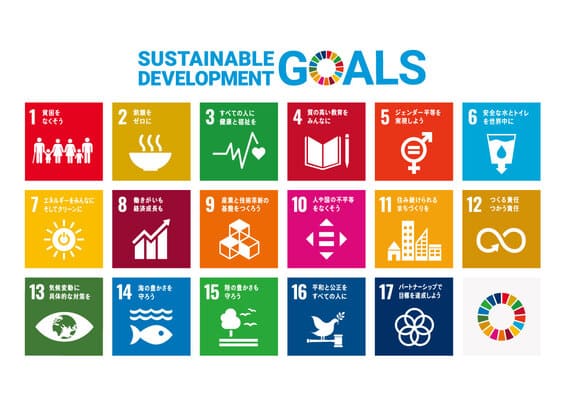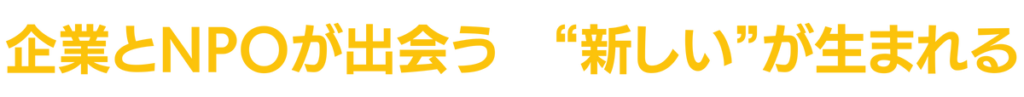
「鉄からはじまった。サステナブルに鉄資源を使い続けるために…」三井 陽介氏(株式会社ミツイバウ・マテリアル代表取締役社長)
鉄からはじまった。サステナブルに鉄資源を使い続けるために…
三井 陽介氏(株式会社ミツイバウ・マテリアル代表取締役社長)
なべ、やかんから始まった

弊社は建築資材の卸売業が本業です。一次商社から材料を買って加工した、鉄の屋根や外壁を製造販売しています。そしてメーカーでもあり、各種メーカーの代理店もしています。
創業は1951年です。創業者の祖父は、鍋やヤカンを仕入れ、松阪市新町で販売していました。2代目である父が機械を導入し、仕入れた鉄を自社で加工製造する事業を始め、父の代に事業を拡大していきました。1991年に祖父から父に代わり、2018年から父と一緒に私が代表をしていましたが、2021年から私一人が代表になっています。
職人とともに 製造から施工まで

2010年に、私はこの会社に戻りましたが、その頃は8割が材料販売をしていました。販売だけでは厳しかったので、施工管理までできる体制に変えていこうと思い、弊社から材料を買っていた職人様に施工を一緒にしませんかと呼びかけ、2014年「安全衛生協力会」という組織を立ち上げました。ベテランの職人は技術があるのですが、営業をする機会が少ないので弊社が営業を受け持ちます。職人様は仕事にこだわりがあり、やり方や品質も違います。こういった技術を継承していけるように組織を作りました。
ひとり親方が多く、保険をかけていない場合も多いので、弊社の工事をして頂く職人様を守る為に保険をかけました。また、元請に対して品質を管理しています。今年で11年目ですが、当初29社で始めた会が今は70社ほどになっています。2割程度であった施工の売り上げがどんどん伸び、今は施工が売り上げの半分以上となり、メインになってきています。主に扱っているのは住宅、商業施設の建築資材ですが、施工管理まで行うようになり、屋根や外壁の工事のサブコンとして、ゼネコンやハウスメーカーの屋根や外壁工事を受けるようになりました。自社で設計提案し、製造、配送、施工までワンストップで行えるのが弊社の特徴です。
弊社が主に扱っているものは、カラーガルバリウム鋼板といって塗装がされている鋼板です。(淀川製鋼、JFE鋼板、日本製鉄など)カラー鋼板を塗装する会社の窓口商社を一次商社と言いますが、ここから鋼板を買っています。松阪は名古屋や関西圏に近いので、名古屋か大阪の商社から仕入れています。我々のような材料を扱う会社には、設計士様から「こういう家を建てる際にはどのような商品を使えば良いか」といった相談があります。自社の商品を提案する場合もありますし、メーカーの商品を提案する場合もあります。
鉄の屋根

屋根材に使われる鉄のシェアが伸びています。「鉄は錆びる」イメージがありましたが、扱っているガルバニウム鋼板は約40年前に発売されており、耐久性能が向上して長い年月にわたり品質が維持できます。
約15年前は鉄製品の屋根は新築着工の2割弱程度でしたが、今は約3分の1になっています。瓦の10分の1の重さで圧倒的に軽く、地震に強い優位性があり、耐久性も高く、穴あき保証は10年あり、商品によっては20年保証のある商品もあります。また、ガルバリウム鋼板は加工性が良いため、いろんなデザインの住宅に対応でき、複雑な形状も対応可能で、カラーバリエーションも種類が多いです。
屋根自体が軽いため太陽光発電の重量にも耐え、屋根に穴を開けずに載せられる製品も出ています。時代の流れにより家屋の着工戸数は減っていますが、ガルバリウム鋼板のシェアは増えています。リフォームの場合は約80%がガルバリウム鋼板製の屋根です。断熱材を入れれば熱も解消されるので、屋根も壁もいろんな商品が出ています。工場、体育館、公共建造物、アパート等の施工をしていますが、件数は住宅が圧倒的に多いです。我々のお客様は、ハウスメーカーや工務店もありますが、建築板金の職人がメインのお客様です。我々の業界は三重県には10社もなく、体育館のような20、30メートルという大型建造物を現場で、自社で加工・成型できるのは、三重県では弊社だけです。
これからの業界のありかた

最近、県外からの依頼があった有名な建物では福井の「恐竜博物館」を施工しました。メーカーの要請で県外に行くことも増えてきて、全国の同業他社と協力して事業を行うこともあります。どの業界も同じだと思いますが、会社の数が毎年減っていて、廃業もあれば、最近はM&Aで一次メーカーの統合もあります。日本の人口が減り、市場も減っていく。業者の数も減ります。しかし、技術は継承していかないといけない。そのため、同業他社の若手経営者と協力しあうことを話しています。私と同年代の経営者は同じ課題意識を持っていて、三重県であれば弊社が施工をしたり、県外の時には材料を貸し借りしながら応援しあうなど、時代の変化のなかで今後はこのようなスタイルになっていくのではないかと思っています。
外国から材料が入ってきて市場が安値になる懸念はあります。その場合には海外に負けない技術を持つしかない。内装材は外国材が入っています。外装材は10年以上前に外国材が一時入りましたが、やはりすぐ錆びるという問題が出ました。最近はかなり品質がよくなっていますが10年後はどうなるかわからないです。10年の実績が出て初めて使用できるかどうか決まりますが、外装の分野ではリスクが大きいので簡単には外国材に変わらないと思います。
厳しい鉄業界、新たな挑戦も
鉄をつくるときに、高炉から二酸化炭素が大量に出ます。電炉に替えるためには古い工場を建て替えたり、ラインの調整をしたりなどお金がかかります。大手メーカーがラインを変えるなどをしてサステナブルな材料だとアピールをしますが、かなり費用がかかります。二酸化炭素を減らすことは必要ですがコストとの兼ね合いがあります。
また、この5年ほどで鉄の仕入価格が倍になっているものもあります。しかし売り値は倍にできない。経営者は我慢するしかないです。売値は適正価格にするしかなく、お客様に理解していただくしかありません。
一方で新しい事業も始めています。海外事業です。ベトナムに会社を作りました。ベトナムを調査したのですが、我々の業界では、ベトナムに日本の技術を持っている会社はまだ少ないので、日本の技術をベトナムで活かそうと考えています。弊社には20年ぐらい前、父の代からベトナムの実習生が来ています。彼らはすごく頑張ってくれて現場でもとても優秀です。日本語学習には力を入れていて、日本語検定も今ではN1を取得した社員もいます。日本語が話せると周りとの関係も良くなり、お客様との会話もできるようになります。ベトナム人は技能実習生と特定技能実習生あわせて16名です。留学生も1人います。技能実習制度は本来、母国に帰って技能実習で得た技術を活かすことです。しかし、技術を活かせる就職先がベトナムには少ないので、ベトナムでの会社設立を3年以上前から準備していました。2025年の1月にようやく会社を設立できました。工場建設に向けてあと2年ぐらいかかると思いますが、面談の際に、ベトナム工場が完成するまで日本で働きたいと話してくれているので、ベトナムの幹部社員になってほしいと思っています。

他にも海外の社員はネパール人が2人います。以前はベトナムの人を中心にして考えていたのですが、最近は特にベトナムだけというわけではないと思ってます。ダイバーシティ経営は、この業界では珍しいです。弊社は社員の約20%が外国人です。女性も約20%、60歳以上の方が約15%です。最近は、障がい者雇用もはじめて、モニス認定を取得しました。誰でも働ける会社にしたいと思っています。常時雇用している人数は80人以上おり、うち正社員は68人です。
なぜSDGsに取組むことに?
基本方針の中で「社員の幸福」を1番上に掲げ、まず「社員の幸福」から考え始めました。社員の働き方改革や残業を減らすことが、世の中で言われ出しましたが、弊社でも「労働時間を減らしても儲かる仕組みをつくること」がワーク・ライフ・バランスだと考え、2016年に全部署から社員を1人ずつ集めて「ワーク・ライフ・バランス委員会」を作り、どうしたら効率よく仕事ができるようになるかについて意見を交わしました。仕事と家庭の両立を考えて、少しずつ社内環境も良くなりました。

2019年頃、ワーク・ライフ・バランス委員会では、社内のことだけになってしまうので、地域やお客様のことまで考えたSDGsに取り組んだ方がよいのではないかと思い、SDGs委員会に名称変更しました。SDGsの考え方に「持続可能な」とありますが、私は「今のものにお金をかけて環境に良いことをするのは間違っている。まずは意識を変えるだけでできることから取り組み、変えられることからやっていこう」と考えました。「SDGsをやっています」とPRしてそれで終わりではダメですし、続けなければ意味がない。改善しながらやっていくべきだと思いました。
最初は、私が主導で始めましたが、社員からの提案でゴミ分別をしていったほうがいいのではないかという提案が出たりするようになりました。そして、徐々に習慣化し、日頃から実践できるようになりました。社員は全員、SDGsを唱和できると思います。環境意識が高まって行動が変わったという社員もいます。環境に優しいことをするのは企業として当たり前ですし、SDGsだからというわけではありません。SDGsを無理に意識しているのではなく、やっていて当たり前という感じで自然に取り組んでいます。
お客さまからリフォームや雨漏りを修繕する依頼があった時に、「断熱材を入れたら断熱効果が上がります」と提案しても、10年前は9割の方が雨漏りだけ直してくれれば良いと言われました。今は半分程度の方が断熱改修も行います。職場環境の改善と電気代の抑制という2つの理由から急に増えました。弊社は昔からやっていたのでノウハウもあり、弊社にしか提案できないこともたくさんあります。環境が良くなって、今まで空調服を着て作業をしていた方が、空調服を着なくても作業ができるようになったと聞いたらすごく嬉しいんです。
弊社の基本方針の一つに「地域に貢献しよう」があり、地域を盛りあげるための協賛をしています。三重高校ダンス部やフットサルチームのスポンサーや、三重県こどもの城の「キッズおしごと広場」での子ども向けの就労体験として「屋根葺き体験」を提供しています。本物の屋根の模型で施工を体験します。とても人気のあるイベントで10時オープンですが、朝7時から並んで今では1000人以上の参加があるそうです。弊社ブースも1日5回、各4名の募集ですが、各回ともすぐにうまってしまいます。地域の祭りやマラソン大会にも参加しますが、社員は仕事として参加するので代休を取れるようにしています。
災害については、ペットボトルを1000本ぐらい常備したり、備蓄品は分けることができるように多めに蓄えています。今考えているのは、2階から屋上にあがれる天井口を設置して避難場所にできるようにしようと検討しています。

ペレットストーブ販売事業
弊社は2010年にISO14001を取りました。その頃から「リフォームするなら環境に優しいエコリフォーム」と掲げてきました。父には、鉄の業界以外に違う事業の柱を作りたいという思いがあったようで「ペレットストーブ」に着目しました。父が中小企業同友会の環境整備委員長の時に、当時イタリアで普及していた捨てられる木材をペレット状の燃料にしたストーブを知り、視察に行き勉強をしました。ヨーロッパは環境への意識が高く、イタリアではペレットストーブがよく使われていたのでイタリア企業の代理店を始めました。薪ストーブは高額で新築住宅でないと設置が難しいですが、ペレットストーブはリフォームで設置することができます。
森林資源が多い日本は、木を適正利用できるバイオマスエネルギーのチャンスがあると思います。環境への配慮としては良い技術だと思っています。薪と違ってほぼ100%燃焼するので煙はほとんど出ません。ペレットは日本の木でつくられたものを販売しています。質の良い京都のものを仕入れて販売しています。三重産のペレットは大量には作れないのですが、自社用には伊勢のものを少し分けていただいています。
パープルはイメージカラー
ミツイバウの社員が来ているポロシャツのカラーは紫色。社用車も紫色。なぜ?
祖父がトラックの色を紫色にしたので、会社のイメージカラーが紫色になったみたいです。私はコーポレートカラーがとても大事だと思っています。ずっと紫色なのでこれで統一することにしました。紫色は祖父の案で「高貴な色」だということもあるようです。目立つから悪いことできないよね、と笑っています。

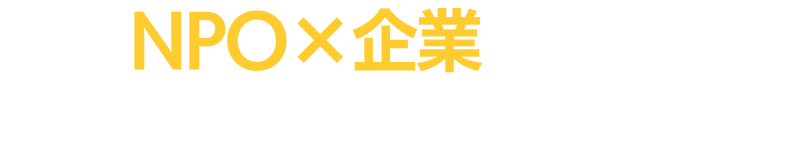

-1-300x300.jpg)