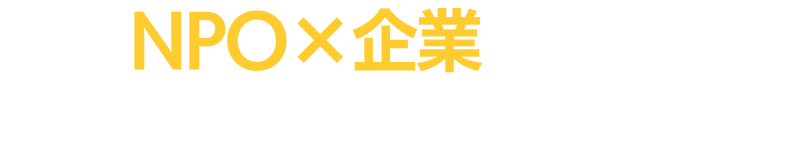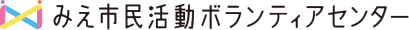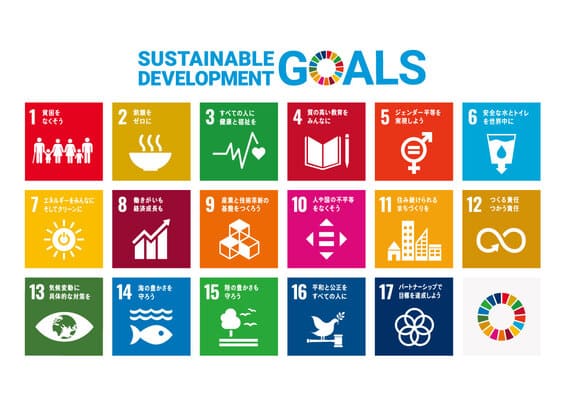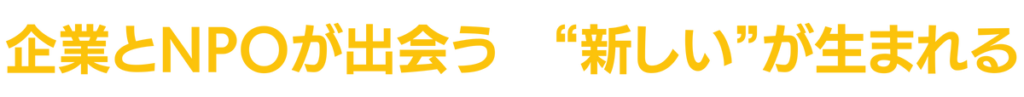
「“もったいない”を“ありがたい”に~人と人とのつながりが強まる地域へ~」杉岡 雪子 氏(イーナバリ株式会社 代表取締役)
“もったいない”を“ありがたい”に
~人と人とのつながりが強まる地域へ~
杉岡 雪子 氏(イーナバリ株式会社 代表取締役)
山々に囲まれた名張市の風景に、ブドウ園が美しく連なっています。取材に訪れた時がまさにブドウの季節。ブドウ販売店が道路際にいくつもありました。ブドウなど地域の食材を「大切」に加工し、製造して販売をしている会社を取材しました。
もったいない、から始まった
-867x1024.jpg)
名張市ではブドウやトマトといった作物が特産品として栽培されています。特にブドウは青蓮寺湖観光村の観光農園が7月20日頃に開園し、10月末頃までの約3か月間、観光客に開放されます。シーズンが終わってもブドウは実るのですが、一房の実の数が減るために販売できなくなってしまいます。果実は熟していて美味しいのでもったいないのですが、農家さんは次のシーズンに向けて、残った果実を切り落とすこともしばしば。選別をする時間がない時などは廃棄にしてしまうそうです。また、今年のように雨が少ないと、果実に十分な水分が行き渡らず、干しブドウのようにしぼんでしまう房もあって、これももったいないです。
なんとかこういった果実を有効活用できないかと考えました。
地域の農産物を加工食品にする!
2014年に名張市が厚生労働省の交付金を活用して「雇用創造協議会(以下、協議会)」を立ち上げました。協議会はその名の通り、地域に雇用を生み出し、地域を活性化することを目的に事業を展開しました。私は協議会の職員になり、「食」をテーマにした事業を担当しました。事業のなかで興味をもったことが「廃棄される食材を加工して販売することができないか」でした。食べられるものを捨てるなんてもったいない。農家さんが一生懸命に育てた思いや農家さんに少しでも収入があれば、みんながハッピーになれると思ったんです。そこで、長期間保存できる加工食品づくりにチャレンジしました。観光客のお土産にもなり、農家さんの収入源にもなる。農業の活性化、雇用の活性化、地域活性化につながると「地元の農産物の加工品を製造・販売する」仕組みづくりを目指しました。

会社をつくる。
2017年1月イーナバリ株式会社を設立し、4月に加工所を整備しました。もう8年が経ちます。
“もったいない”を“ありがたい”に変えていく流れをつくり、地元のブドウ農家さんやイチゴ農家さんなどの生産者さんと継続的な関係が生まれました。ブドウ農家さんとは、規格外のブドウをジャムやジュースに加工したり、素材の活用としてそのままパン屋さんやケーキ屋さんに提供したりしています。
廃棄処分されるタケノコを利用した商品もつくりました。名張市は竹林が多く、タケノコの時期になると大量に出回り、販売しきることができません。最初はタケノコの水煮を商品にしました。しかし、水煮も売れ残るようになり…。今は、タケノコご飯の素、タケノコ入りちらし寿司の素、タケノコ入りレトルトカレーを開発し販売しています。
地元の食材を使った商品は、味の調整からパッケージ企画まですべて社内で行っています。社員は5名。「自分たちが買いたいと思う味」を追求したレシピを考え、試作を重ね、納得したものだけを商品化しています。スタッフは地域のことをよく知っているので、地元ならではの強みを活かし、地元の歴史や文化を大切にした加工品づくりに取り組んでいます。地元商品のパッケージデザインは名張市在住のデザイナーが担当しています。
最近は「ジン」の開発をしています。名張産のジュニパーベリー(ネズミサシの実)、ユズや山椒など香り高い農産物を蒸留酒の香料にして地元のお酒をつくり、地元の魅力を発信する取組みです。この商品も地元の農業を支え、ネズミサシやユズなどの作付け、農地の維持につながっています。

地域から全国、海外に。委託加工まで…。
-1024x1024.jpg)
当社の商品は地元の直売所や名張市内のスーパー内の地産地消コーナーなどに置いています。
当初、ホームページは不要だと考えていましたが、「発信することも大切だよ」とのアドバイスがあり、ホームページを開設しました。そのおかげで、ネット販売やふるさと納税の返礼品など全国に展開されました。
販売効果だけではなく、ホームページを見て、全国、海外から「同じような課題があります」と声が届くようになり、加工食品の委託製造の依頼が増えました。「捨てるのではなく、活用すること」。私たちと同じ志を持つ人からの相談や問合わせです。
尼崎市の特産品である「尼芋(あまいも)」を利用した商品を作りました。傷がついたり収穫量が十分でなかったりなどでスーパーなど市場に出すことができない美味しい尼芋をペーストに加工して納品しました。「大阪なんばネギ」を利用した製品もつくりました。ネギの先が少し黄色くなっただけで出荷できないネギは、関西万博で販売する「ネギ入りおにぎり」に活用されたり、ネギを一旦乾燥加工させて味噌玉に混ぜ、お湯を注げばお味噌汁になる「味噌玉」のための乾燥ネギを製造しました。スーパーで売れないものも加工すれば十分に価値を持ちます。
海外からの依頼もあり、海外産の雑穀米を使用したお粥の加工を請け負いました。三重県の会社が離乳食ブランド商品として販売しているお粥には、お米に魚のほぐし身や野菜のみじん切りを加え、レトルト加工することで、赤ちゃんが安心して食べられる一品に仕上げました。
玉ねぎの皮やサツマイモの皮など、通常なら廃棄されるものも出汁や乾燥パウダーとしての利用価値があります。「どう使うことができるか」「どうすれば現実的にビジネスとして成り立つか」を社員とアイデアを出しあって商品開発をしています。
主に農産物を中心にしていますが、肉や魚などを使った食品加工についての相談も増えています。すべてに対応できるわけではありませんが、食品衛生法に基づいて処理された食材であればなど、条件を整えて引き受けることもあります。
理想的な循環型の取引が少しずつ実現しています。小ロット・低コストで未利用食材を有効活用できる体制を整えているところです。販売している商品のうち8~9割は委託加工の商品です。いろいろな案件が全国から入ってくるので、自社商品の販売は年に数回行う程度になりました。大切にしていることは「委託加工か、自社製品か」ではなく、「食べられるものを捨てずに活かすこと」です。
「地元のために始めたこと」が「全国、海外から必要とされる存在」になれるよう、丁寧に続けていきたいと思っています。
こだわりの加工方法、試行錯誤の日々
「体は食べ物からできているんだから、“ちゃんとしたもの”を食べなさい。」
子どもの頃からの母の口癖でした。“ちゃんとしたもの”というのは、高級なものという意味ではなく、“丁寧に育てられた安心できるもの”です。日本には昔からの「天日干し」「酢漬け」「加熱による殺菌」など、添加物を使わずに長期保存が可能な“知恵”がたくさんあります。そういった伝統技術を、現代の食品衛生法にあう形で生かし、「なるべく食材そのものの味・良さを届けたい」という気持ちで取り組んでいます。
理想と現実のギャップも痛感しています。自然な形、自然を生かした技術を使ってていねいに製造する商品の値段はどうしても高くなってしまいます。オーガニックや無添加志向の商品の価格設定はとても難しい。少し高くても信頼できるものを買いたい、という消費者に支えられて、事業を継続しています。「商品の価値」が少しずつ理解されてはいますが、まだまだ購入してくださる消費者が少ないのが現実です。

安定的に材料を確保することも課題です。農産物は天候の影響を大きく受けるため、「たくさん欲しい」という要望に応えられないことがあります。季節限定の商品については「もうないの?」と問い合わせいただくこともしばしばあります。特に旬の食材はその時期にしか収穫できず、加工し、ストックして地元の販売店で売っていますが、売り切れてしまうと製造することができません。
また、委託加工の場合は「収穫した農産物を今すぐ加工してほしい」と言われることが多いのですが、他の加工・製造予定が入っているとお引き受けできないことがあります。大型冷凍庫を導入して、冷凍保存ができる果物は保管できるようになりました。少しずつ対応力をあげています。
名張への思い~未来を見据えて地域に根ざす
地元・名張に深い思い入れがあります。母は地域の川を守る運動や保育所づくり、配食サービスを先駆けて実施するなど地域活動に尽力しました。その思いを引き継ぐ形でこの仕事をしています。事業の原点は「地域を支えたい」という思いです。ビジネス的な成功だけがゴールではありません。名張、日本、世界と同じ志を持つ仲間とつながり、課題解決を一緒に目指す。そんな広がりをつくっていきたい。最終的に目指すのは、「作る人」「使う人」「届ける人」がともに笑顔でいられる社会です。未利用食材が生まれ変わり、人と人とのつながりが強まる、そんな未来を見据えながら、これからも地域に根ざした加工業を続けていきたいと考えています。